- コラム
【コラム】「抗がん剤=つらい」? 犬・猫の抗がん剤治療のホントのところ
「うちの子に抗がん剤なんて、本当に大丈夫?」そんな不安を抱える飼い主さんは少なくありません。
「抗がん剤」と聞くと、「つらい」「副作用が強い」といったイメージを持たれることが多いですが、動物医療では、副作用をできるだけ抑えながら、ワンちゃん・猫ちゃんが快適に過ごせる時間(=生活の質、QOL)を伸ばすことを目的とすることが多いです。
今回は、犬や猫の抗がん剤治療についてわかりやすくご紹介します。
抗がん剤治療とは?
がんは、体の中の細胞が異常に増え続けることでできる「悪性の腫瘍」です。
ワンちゃん・猫ちゃんのがん治療には、大きく分けて次の3つの方法があります。
- 外科手術
- 放射線治療
- 抗がん剤治療
抗がん剤治療は、注射や飲み薬で薬を全身に届けて、がん細胞の増殖を抑えたり、腫瘍を小さくしたりすることを目的としています。手術や放射線が「目に見えるがん(局所)」を狙う治療なのに対し、抗がん剤は全身に広がったがん細胞や、まだ見つかっていない転移したがんに対しても作用する点が特徴です。
ただし、抗がん剤だけでがんを完全に治すのは難しく、大きな腫瘍を小さくすることは難しいケースもあります。そのため、抗がん剤治療は「がんを目に見えないくらい小さくすること(=寛解)」や、「進行を遅らせて生活の質を保つこと」が主な目的となります。
抗がん剤が使われる病気とその効果
抗がん剤は、次のようながんで使われることがあります:
- リンパ腫
- 白血病
- 肥満細胞腫
- 移行上皮がん(膀胱のがんなど)
- 骨肉腫(骨のがん)
- 乳腺腫瘍(手術後の再発予防として)
抗がん剤は、がんが全身に広がっていたり、手術だけでは取りきれないケース、あるいは再発や転移のリスクが高いがんに対して、抗がん剤治療は大きな効果を発揮することがあります。たとえばリンパ腫や白血病など、体のあちこちに影響するタイプのがんでは外科手術が難しいため、抗がん剤が第一選択になります。また、乳腺腫瘍や骨肉腫などでは、手術後に再発や転移を防ぐ目的で使用されます。
具体例として、犬のリンパ腫では、治療をしない場合は平均で約1か月の余命とされていますが、抗がん剤治療を行うことで平均1年ほどに延び、2年以上元気に過ごせる子もいます。
ただし、すべてのがんに抗がん剤が有効とは限りません。動物医療では人に比べてまだデータが少ない面もあるため、治療法の選択はがんの種類や体調、ご家族の希望に応じて慎重に判断していく必要があります。
人とは違う犬や猫の抗がん剤治療
「抗がん剤=つらい治療」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。たしかに人の医療では、がんの完治を目指して高用量の抗がん剤を使うため、副作用が出ることを前提に治療が行われることも少なくありません。しかし、動物医療では「がんを治す」ことよりも、「元気で穏やかな生活を少しでも長く続ける」ことを目的としています。そのため、副作用ができるだけ出ないように、抗がん剤の量や使い方をしっかり調整して治療を行います。多くの子が、治療中でも普段通りに元気に過ごしています。治療は通院でできることがほとんどで、入院が必要になるケースはごくわずかです。
犬や猫に使われる抗がん剤の種類
動物に使う抗がん剤には、注射・点滴・飲み薬のタイプがあり、当院では10種類ほどを取り扱っています。抗がん剤は、1種類だけでは十分な効果が出にくいこともあります。がんの種類によって薬の効き方が違うため、いくつかの薬を順番に組み合わせて使う「プロトコル治療(多剤併用)」がよく行われます。たとえば「CHOP療法」と呼ばれる方法は、リンパ腫の治療によく使われる有名なプロトコルです。
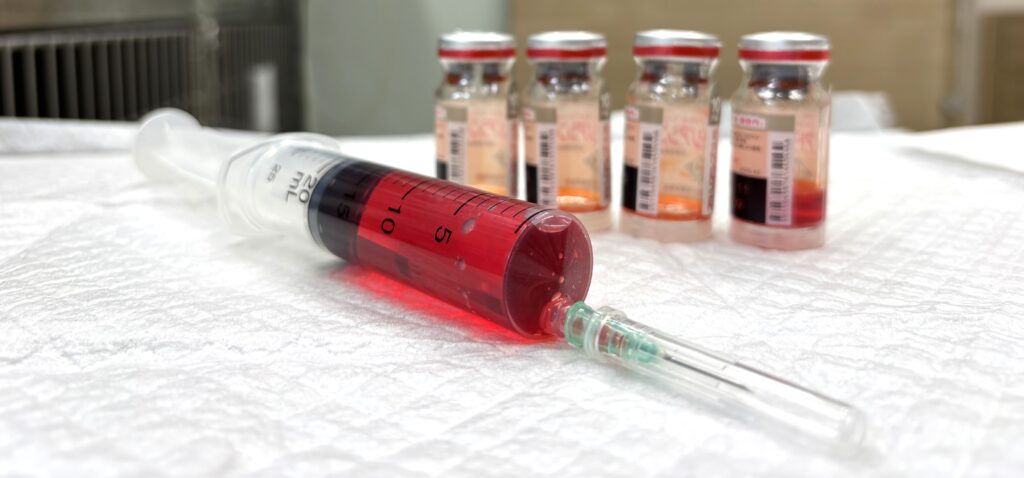
治療方法と通院ペース
抗がん剤治療の通院は、がんの種類や体の状態によって違いますが、1〜3週間に1回のペースが一般的です。
治療の前には必ず、身体検査と血液検査を行って、白血球の数や肝臓・腎臓の状態をチェックします。白血球が少なすぎるなど問題がある場合は、抗がん剤の投与を延期したり、量を減らしたりして体への負担を減らす工夫をします。必要に応じて、超音波検査(エコー)やレントゲン検査を行うこともあります。
検査で問題がなければ、抗がん剤を投与します。いちばん多いのは、点滴や注射で静脈から投与する方法です。一部の薬は、皮下(皮ふの下)や筋肉に打つこともあります。お薬によってかかる時間は違いますが、数十分〜数時間程度です。午前にお預かり・夕方お迎えになることもあります。飲み薬(内服薬)を使う場合は、体調や検査結果を見ながら獣医師が判断し、ご自宅で飲ませていただきます。
抗がん剤の副作用
抗がん剤は、「分裂している細胞」に作用する薬です。そのため、がん細胞だけでなく、骨髄・腸粘膜・毛根などの、普段から分裂を繰り返している正常な細胞にも影響が出ることがあります。
主な副作用には次のようなものがあります:
- 消化器の症状(吐き気・食欲低下など)
抗がん剤を打った当日から2日くらいの間に、軽い吐き気や食欲の低下が出ることがあります。多くの場合は軽いもので、吐き気止めや下痢止めのお薬をあらかじめ処方することで予防できます。 - 免疫力の低下(骨髄抑制)
抗がん剤の影響で、1週間ほど後に白血球が減ることがあります。白血球は体を細菌から守る働きがあるため、数が減ると感染症のリスクが高くなります。まれに、急な発熱やぐったりした様子になる「敗血症」という状態になることもあるため、抗がん剤治療中は定期的な血液検査で白血球の数をチェックします。 - 毛が抜ける・毛が薄くなる
一部の犬種(プードルやシュナウザーなど)では、毛が薄くなったり抜けたりすることがありますが、ほとんどの子では気にならない程度です。
副作用の出方には個体差がありますが、抗がん剤の量を調整することで副作用を抑えることが可能です。実際には、多くの子が副作用なし、もしくは軽い症状ですみます。もし副作用が強く出た場合も、次回の治療では量を調節して、その子に合った治療法を探していきます。
飼い主さんにできること
動物たちは、体の不調を言葉で伝えることができません。だからこそ、いつもそばにいる飼い主さんの気づきがとても大切です。抗がん剤治療を受けているワンちゃん・猫ちゃんのために、次のようなサポートをお願いします:
- 食欲や元気、排泄の様子を毎日チェックする
- いつもと違う様子があれば、すぐにご相談ください
- 通院のときは声をかけて安心させてあげましょう
- お薬(飲み薬)を忘れずに、決められた時間にあげましょう
治療の内容によっては、抗がん剤の飲み薬をご自宅で与えていただく場合もあります。抗がん剤は人にも影響が出る可能性があるため、お薬に直接触れないようにすること、排泄物の取り扱いにも注意することが必要です。

抗がん剤治療は、がんの進行を抑え、痛みの少ない時間をできるだけ長く保つための選択肢のひとつです。副作用のコントロールや治療の継続も含め、飼い主さんとの二人三脚がとても大切です。抗がん剤治療を始めるか、継続するか、終了するかは、ご家族にとって大きな決断です。当院では、治療を無理におすすめすることはありません。年齢や性格、生活環境、持病の有無、費用や通院の負担など、さまざまなことを考えながら、ワンちゃん・猫ちゃん、そしてご家族にとって、何がいちばん良い選択なのかを一緒に考えていきましょう。
「うちの子に抗がん剤って必要?」「どんな治療なのか話だけでも聞いてみたい」──そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。

